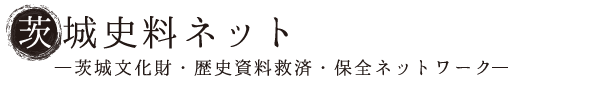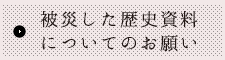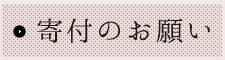それぞれリンクをクリックしてご覧下さい。
最新のお知らせ
2020.10 茨城史料ネット活動再開のお知らせ
茨城史料ネットでは、10月28日(水)から活動を再開いたします。
ただし、参加者を学内の教員・学生に限り、学外からの参加受付についてはひとまず見送ることにしました。
学外の皆様におかれましては、このまま感染拡大が収束し、安心して参加していただける環境が整った段階で
改めてご案内させていただきますので、それまでしばらくお待ちいただけますと幸いです。
私たちの活動を温かく見守っていただいている皆様のお気持ちを思うと心苦しい限りですが、どうかご理解ください。
2020.2 茨城史料ネット 東日本大震災被災資料対応完了のご報告
日頃より、茨城史料ネットの活動にご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。茨城史料ネットは、東日本大震災の後、今日まで主に民間に伝えられてきた歴史資料の消失を食い止め、保全の手立てを講じ、その価値を地域住民に伝える活動を続けていました。被災地で救済にかかわった資料は数万点に及びます。茨城大学から活動場所の提供を受け、資料を一点一点クリーニングし、記録保存のための写真撮影を行い、資料目録を作成するという、とても息の長い地道な作業を主に担ったのは、同大学の大学院生・学生たちでした。8年半に及ぶ活動により、膨大な作業も少しずつ進捗し、多くの被災資料が保全・記録され、所蔵者や新たな寄託先に返っていきました。
震災から9年目を迎える3月を前に、最後まで残っていた資料の保全・整理作業が終了し、所蔵者に返却の運びとなりました。ここに東日本大震災被災資料への対応がひとまず完結することとなりますので、ご支援いただいた皆様にご報告し、深甚なる謝意を捧げたいと思います。ありがとうございました。
もちろん茨城史料ネットの活動自体がこれで終了するわけではありません。双葉町で福島第一原発事故の放射能に汚染された資料の保全活動にも引き続き協力していきます。また震災後に発生した自然災害に伴う被災資料や、地域で管理の難しくなった資料が次々にわれわれの手に委ねられる現状もあります。ここを一つの節目とし、さらに体制を整え、立場を越えて多くの方々と手を携えつつ、責任を果たしていく所存です。今後とも、よろしくお願いします。
2019.10 水戸市内の被災史料対応に関するお知らせ
水戸市立博物館・茨城史料ネットでは、台風19号により被災した歴史資料の相談を受け付けています。なお、詳細につきましては下記のページをご覧下さい。
水戸市立博物館公式ホームページ
2019.10 豪雨災害発生にあたってのお知らせ
台風19号がもたらした豪雨による被害を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
まだ被害の全容はわかりませんが、今後、茨城県および周辺都県における文化財・歴史資料への被害についての情報も、次第に明らかになるものと予想されます。茨城史料ネットでは、微力ではありますが、被災地の文化財・歴史資料の保全に、可能な限り支援をしていきたいと思います。
どのような些細なことでも構いませんので、ご遠慮なくご相談ください。また周囲に被災の情報などあれば、どうぞお寄せください。
被災地の被害がこれ以上広がらないこと、復興が一日も早く進むことを、心よりお祈り申し上げます。
茨城史料ネット代表 高橋修
過去のお知らせ
|
 2019.2 第14回茨城大学人文社会科学部 地域史シンポジウム「茨城における戦争の記憶とその継承」開催のご案内 2019.2 第14回茨城大学人文社会科学部 地域史シンポジウム「茨城における戦争の記憶とその継承」開催のご案内
2019年2月3日(日)、茨城大学人文社会科学部講義棟 10番教室(於:茨城県水戸市文京)にて、第14回茨城大学人文社会科学部 地域史シンポジウム「茨城における戦争の記憶とその継承」が開催されます。
本シンポジウムは当団体が後援するものです。茨城県内の戦争遺跡や展示施設、記念碑、記憶の継承の活動や実践について紹介・検討し議論を深めていきます。どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。シンポジウムに関する詳細は、下記をご覧ください。
地域史シンポジウム「茨城における戦争の記憶とその継承」
○日時:平成31年2月3日(土) 13時30分~17時
○会場:茨城大学人文社会科学部講義棟 10番教室(茨城県水戸市文京2-1-1)
○入場:無料・事前申し込み不要
内容:【基調報告】「地域における戦争体験――多様性とその継承について」
柳沢遊(慶應義塾大学名誉教授)
【個別報告】「北茨城における風船爆弾(陸軍)と第一四一特攻艇「震洋」(海軍)について」
丹賢一(郷土史研究家)
【個別報告】「戦時下の茨城県朝鮮人と日立鉱山」
張泳祚(茨城県朝鮮人戦争犠牲者慰霊塔管理委員会事務局長)
【個別報告】「戦跡の活用と戦争の記憶の継承について」
金澤大介(筑波海軍航空隊記念館館長)
【個別報告】「茨城県内における戦争モニュメント調査報告」
茨城大学人文社会科学部日本近現代史ゼミ
○お問合せ:茨城大学人文社会科学部 佐々木啓研究室
Mail:kei.saaki.1020@vc.ibaraki.ac.jp
|
|
 2017.1 人間文化研究機構広領域型基幹研究プロジェクト国文学研究資料館ユニット「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究」シンポジウム「地域歴史資料救出の先へ」開催のご案内 2017.1 人間文化研究機構広領域型基幹研究プロジェクト国文学研究資料館ユニット「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究」シンポジウム「地域歴史資料救出の先へ」開催のご案内
2017年9月2日(土)、いわき市文化センター 大ホール(於:福島県いわき市)にて、人間文化研究機構広領域型基幹研究プロジェクト国文学研究資料館ユニット「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究」シンポジウム「地域歴史資料救出の先へ」が開催されます。
本シンポジウムは福島県内の歴史資料の保全と継承に関するものです。当会関係では副代表の白井哲哉筑波大教授、当会の活動にご支援・ご協力をいただいております西村慎太郎国文学研究資料館准教授、当会事務局OBの泉田邦彦氏が講演されます。また当会も本シンポジウムに後援として協力させていただいております。どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。シンポジウムに関する詳細は、下記をご覧ください。
シンポジウム「地域歴史資料救出の先へ」
○日時:平成29年9月2日(土) 13時~17時(開場12:30)
○会場:いわき市文化センター 大ホール (福島県いわき市平字堂根1-4)
○入場:無料・事前申し込み不要
内容:【第1報告】「民俗資料の保全をめぐる限界と可能性―福島県における民具の救出を事例に―」
内山大介氏(福島県立博物館主任学芸員)
【第2報告】「「地域の記憶」を記録する―浪江町請戸地区における大字誌編纂の取り組み―」
泉田邦彦氏(東北大学大学院生)
【第3報告】「救出した歴史資料の射程―福島県浜通りから未来へ―」
西村慎太郎氏 (国文学研究資料館准教授)
【第4報告】「被災の記憶と資料を未来へ伝える試み―双葉町と筑波大学の震災資料保全活動―」
白井哲哉氏(筑波大学教授)
○お問合せ:大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国文学研究資料館
TEL:050-5533-2900(国文学研究資料館代表)
Mail:s.nishimura@nijl.ac.jp(国文学研究資料館 西村慎太郎)
なお、展示に関する詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国文学研究資料館
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇シンポジウム「地域歴史資料救出の先へ」チラシ(JPEGファイル))
|
|
 2017.6 ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」開催のご案内 2017.6 ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」開催のご案内
2017年7月11日(火)~11月5日(日)、茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ(於:栃木県茂木町)にて、ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」が開催されます。
平成24年(2012)7月、茨城史料ネットは、歴史資料ネットワークをはじめとする全国の史料ネットや個人のボランティアと連携して、栃木県茂木町の旧島﨑家から資料レスキューをおこないました。旧島﨑家は元禄時代から続いた近江商人の出店で、土蔵や母屋には経営関係文書をはじめとした膨大な量の歴史資料が残されていました。茨城史料ネットは茂木町からの依頼をうけ、2日間かけて資料を搬出し、同年9月から翌年3月までかけておよそ1万1千点の整理を終えました。
旧島﨑家の跡地には、平成28年7月16日に図書館を中心とした文化施設「ふみの森もてぎ」がオープンし、茂木町の文化・交流における新たな拠点として運営されています。島崎家資料の管理と公開、そして未整理資料の整理も同館が担うことになりました。造り酒屋であった旧島﨑家の仕込み蔵は、移築復元し「ギャラリーふくろう」として、質蔵は曳家して移築し「ギャラリー質蔵」として、町民の作品展示や、イベントの開催場所として利用されています。
また、図書館内には歴史資料展示室が設置され、茂木町の歴史を紹介する企画展示が開催されています。今年の7月11日からは、ふみの森開館1周年を記念して、特別展「帰ってきた島﨑雲圃」が開催されます。雲圃は旧島﨑家の3代目で、商家の当主を務めるかたわら、画人としても活動しました。今回の記念展では、島﨑家・茂木町が栃木県立美術館に寄託してきた、雲圃や弟子の小泉斐らの絵画が、前期・後期に分けて展示されます。
平成24年の資料レスキューの際には、全国各地から多くの皆様に支援を頂きました。茂木町の取り組みは、決してその終着点ではありませんが、行政と民間団体が一体となって取り組んだ資料保存活動の一つの到達点と考えています。ぜひこうした機会に、「ふみの森もてぎ」を見学いただければと思います。
ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」」
○日時:平成29年7月11日(火)~11月5日(日) 9時~19時(土日祝日は18時まで、翌日休館)
○会場:茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ (栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1720-1)
○入場:無料
○内容:【前期】「鮎と語らう」7月11日(火)~9月3日(日)
【後期】「美を遊ぶ」9月12日(火)~11月5日(日)
○お問合せ:茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ
TEL:0285-64-1023
茨城史料ネット事務局(添田仁研究室)
TEL:029-228-8118 Mail:hitoshi.soeda.carp@vc.ibaraki.ac.jp
なお、展示に関する詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」チラシ表面(JPEGファイル))
◇ふみの森もてぎ開館1周年記念特別展「帰ってきた島崎雲圃」チラシ裏面(JPEGファイル))
|
|
 2017.1 第1回ふみの森もてぎ歴史フォーラム「近江商人の知恵とくらし」開催のご案内 2017.1 第1回ふみの森もてぎ歴史フォーラム「近江商人の知恵とくらし」開催のご案内
2017年2月5日(日)、茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ(於:栃木県茂木町)にて、第1回ふみの森もてぎ歴史フォーラム「近江商人の知恵とくらし」が開催されます。
近江商人とは、近江国(滋賀県)を拠点として、日本各地へおもむいて商いをした商人たちのことです。江戸時代はもちろん明治以降も活躍し、大企業にまで成長した家も多くあります。茂木の島﨑家も、そのような近江商人として活躍した旧家です。
島﨑利兵衛家は、元禄16年(1703)に茂木に店をかまえ、主に酒造業で財をなしました。「ふみの森もてぎ」は同家のあと地に建てられ、島﨑家の文化財も茂木町で管理・保管して調査を進めています。しかし、茂木にお住まいのみなさんでも、近江商人や島﨑家について聞いたことはあっても、彼らがどのような商いや生活をしていたのかということはほとんどご存じないのではないでしょうか。
このフォーラムを通じて、茂木で活躍した近江商人を少しでも身近に感じてもらえればと思います。
また1月31日(火)~3月31日(金)にかけて、「近江商人 島﨑利兵衛家」と題した展示が開催されます。こちらでは、江戸・明治期における島﨑家の商いやくらしの様子を物語る古文書や道具類を中心に紹介します。
フォーラム・展示とも、どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。フォーラムに関する詳細は、下記をご覧ください。
第1回ふみの森もてぎ歴史フォーラム「近江商人の知恵とくらし」
○日時:平成29年2月5日(日) 13時~16時30分(12時30分開場)
○会場:茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ ギャラリーふくろう(栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1720-1)
○入場:無料(定員100人、先着順・申し込み不要)
○内容:【基調講演】「近江商人の魅力」
末永國紀氏(同志社大学名誉教授、(財)近江商人郷土館館長)
【講演1】「老舗商家と伝統」
塚原伸治氏(茨城大学人文学部准教授)
【講演2】「島﨑家のたからもの」
須藤千裕氏 (茂木町教育委員会主任)
○お問合せ:茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ(須藤千裕)
TEL:0285-64-1023 Mail:fuminomori@town.motegi.tochigi.jp
茨城史料ネット事務局(添田仁研究室)
TEL:029-228-8118 Mail:hitoshi.soeda.carp@vc.ibaraki.ac.jp
企画展「近江商人 島﨑利兵衛家」
○期間:平成29年1月31日(火)~3月31日(金)
(月曜日休館。祝日の場合は開館し、翌日が休館となります。)
○会場:茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ1階 歴史資料展示室(栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1720-1)
○入場:無料
なお、展示に関する詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
茂木町まちなか文化交流館 ふみの森もてぎ 企画展「近江商人 島﨑利兵衛家」
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇第1回ふみの森もてぎ歴史フォーラム「近江商人の知恵とくらし」チラシ(JPEGファイル))
|
|
 2016.10 「文化財・歴史資料の曝涼・公開」についてお知らせ 2016.10 「文化財・歴史資料の曝涼・公開」についてお知らせ
所蔵者や地元住民自身の手による、虫干しを兼ねた資料の公開を「曝涼(ばくりょう)」と言います。この昔ながらの、ローコストな文化財・歴史資料の保存・公開の方法が、今、茨城県内に広がりつつあり、多くの見学者を集め、学界からも注目されています。
常陸太田市・常陸大宮市に加え、今年度からは笠間市・かすみがうら市でも教育委員会の事業として、連携して開催することになりました。さらに地域における文化財・歴史資料の保存・公開という理念を共有する茨城史料ネットが「文化財・歴史資料の曝涼・公開ネットワーク」としてコーディネートし、茨城大学・茨城キリスト教大学に加え、新たに常磐大学や水戸一高の学生・生徒たちも、解説とおもてなしに協力します。
◆今後の予定◆
【常陸太田市・常陸大宮市】
□「指定文化財 集中曝涼」 平成28年10月15日(土)・16日(日)
常陸太田市ホームページ URL…http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003787.html
問い合わせ 文化課 0294-72-3201
常陸大宮市ホームページ URL…http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002336.html
問い合わせ 歴史民俗資料館 0295-52-1450
【笠間市】
□「かさま文化財公開」 平成28年10月22日(土)・23日(日)
笠間市ホームページ URL… http://www.city.kasama.lg.jp/page/page007687.html
問い合わせ 生涯学習課 0296-77-1101
【かすみがうら市】
□「かすみがうら市指定文化財一斉公開」 平成28年11月12日(土)・13日(日)
かすみがうら市ホームページ 掲載準備中
問合せ 郷土資料館 029-896-0017
|
|
 2016.3 茂木町ふるさと歴史フォーラムⅢ「歴史資料からひもとく戦時下の茂木」開催のご案内 2016.3 茂木町ふるさと歴史フォーラムⅢ「歴史資料からひもとく戦時下の茂木」開催のご案内
2016年3月27日(日)、茨城史料ネットは茂木町教育委員会とともに、一昨年から開催されている「茂木町ふるさと歴史フォーラム」の第三弾として、「歴史資料からひもとく戦時下の茂木」を開催します。
当会は、2012年から栃木県茂木町教育委員会の資料整理を支援し、茂木町の歴史・文化財にかかわる普及事業を支援してきました。今回は、近代という時代をテーマに設定し、茂木町とアジア・太平洋戦争とのかかわりにスポットライトを当て、町の歴史をわかりやすくお伝えするフォーラムを開催するはこびとなりました。
まず、山本和重先生(東海大学)より地域にねむる戦争資料についてご講演をいただきます。あわせて、佐々木啓(当会事務局長補佐)が、十五年戦争と茂木の人々について報告をいたします。
また、同日に特別展示「茂木と戦争―過去の記憶を未来へ―」を開催します。茨城史料ネットのメンバーが随時解説をさせて頂きますので、あわせて御観覧いただければ幸いです。
フォーラム・展示とも、どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。フォーラムに関する詳細は、下記をご覧ください。
茂木町ふるさと歴史フォーラムⅢ「歴史資料からひもとく戦時下の茂木」
○日時:平成28年3月27日(日) 13時~16時
○会場:茂木町民センター 別館ホール(栃木県芳賀郡茂木町字茂木151番)
○入場:無料(先着200名様・申し込み不要)
○内容: 【講演1】「地域にねむる戦争資料―町村役場の兵事書類―」
山本和重氏(東海大学教授)
【講演2】「「十五年戦争」と茂木の人びと」
佐々木啓 (茨城史料ネット事務局長補佐・茨城大学准教授)
○お問合せ:茨城大学人文学部佐々木啓研究室(kei.sasaki.1020@vc.ibaraki.ac.jp)
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇茂木町ふるさと歴史フォーラムチラシ(JPEGファイル))
|
|
 2016.1 新年のごあいさつ 2016.1 新年のごあいさつ
新年、あけましておめでとうございます。
昨年9月の関東・東北豪雨災害により、被害にあわれた皆様には、改めてお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りするとともに、我々も被災地に寄り添い、微力を尽くしてまいりたいと思います。被災資料のレスキュー活動の際には、県内はもとより全国各地からも、たいへん大きなご支援と激励をいただきました。厚く御礼申し上げます。
東日本大震災による被災資料については、学生や市民の奮闘により、大半の整理が終わっていますが、諸般の事情により、いまだ行き先の決まらない救済資料が膨大に残されています。その後も、断続的に民間の歴史資料が持ち込まれており、保全・整理作業の完結はなかなか先が見通せない状況にあります。関東・東北豪雨災害による被災資料のレスキュー活動もまだまだ継続する必要があります。加えて救済した資料の保全のための処理や整理が、まもなく本格化する予定です。
皆様からのご支援無くしては、今後の活動を継続することさえできません。新年の茨城史料ネットの活動にも、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
平成28年(2016)1月1日
茨城史料ネット代表 高橋 修
|
 2015.11 第11回茨城大学人文学部地域史シンポジウム「自然災害に学ぶ 茨城の歴史-被災の記憶と教訓を未来へ-」開催のご案内 2015.11 第11回茨城大学人文学部地域史シンポジウム「自然災害に学ぶ 茨城の歴史-被災の記憶と教訓を未来へ-」開催のご案内
茨城大学人文学部では、2015年12月5日に第11回地域史シンポジウムを開催いたします。
茨城史料ネットは後援団体としてこれに協力しており、副代表の白井哲哉、事務局長の添田仁も登壇することになっております。
年末のお忙しい時期ではございますが、どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。シンポジウムに関する詳細は、下記をご覧ください。
□第11回茨城大学人文学部地域史シンポジウム「自然災害に学ぶ 茨城の歴史-被災の記憶と教訓を未来へ-」
江戸時代は、地震、津波、火山噴火、旱魃、高波、洪水など、数多くの自然災害に悩まされた時代でした。それは、私たちがくらす茨城の地も例外ではありません。私たちの先祖は、自然災害をどのように受けとめ、どのようにして苦難を乗りこえてきたのでしょうか。災害と復興の歴史には、大規模な自然災害が頻発する現代を生きるヒントが隠されているようにも思います。歴史学や地域文化遺産学の最新の研究成果にふれながら、自然災害を通して見えてくる茨城の歴史と未来について、一緒に考えてみませんか。
○日時:平成27年(2015)12月5日(土) 12時30分~17時30分
○会場:茨城大学人文学部人文講義棟10番教室(茨城県水戸市文京2-1-1)
○基調講演:田家(たんげ) 康(やすし) ― 気候で読み解く日本の歴史
※1959年、神奈川県生まれ。(株)農林中金総合研究所客員研究員。
2001年、気象予報士の試験に合格、日本気象予報士会東京支部長。
著書に『気候文明史』(2010年)、『世界史を変えた異常気象』(2011年)、『気候で読み解く日本の歴史』(2013年)、『異常気象が変えた人類の歴史』(2014年)がある。
◇セッション1 江戸時代の災害・復興と民衆
・江戸時代の災害の記録と被災資料 馬場 章(東京大学)
・大地震と江戸庶民-ナマズ・鹿島信仰・鯰絵- 富澤 達三(松戸市立博物館)
◇セッション2 被災の記憶と教訓を未来へ
・関東・東北豪雨水害から文化遺産を救い出す-茨城大学・茨城史料ネットの取り組み- 添田 仁(茨城大学)
・文化財レスキューから歴史まちづくりへ-福島県国見町の取り組みから- 大栗 行貴(国見町教育委員会)
・原子力災害と避難に関する記録の保全と活用 白井 哲哉(筑波大学)
主催 茨城大学人文学部、基盤研究(S)「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立-東日本大震災を踏まえて-」(代表・奥村弘)
後援 茨城県教育委員会、茨城史料ネット、ふくしま史料ネット、茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)、筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター
お問合せ先 添田仁(茨城大学人文学部准教授) hitoshi.soeda.carp@vc.ibaraki.ac.jp/029-228-8118
なお、本企画は、科学研究費補助金・基盤研究(S)「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立-東日本大震災を踏まえて-」(代表・奥村弘)の研究成果の一部です。
□当日のタイムテーブル
11:30 開場
12:30 開会
12:40-13:30 基調講演 田家 康(50分)
13:40-14:20 セッション1 馬場 章(40分)
14:20-15:00 セッション1 富澤達三(40分)
15:10-15:40 セッション2 添田 仁(30分)
15:40-16:00 セッション2 大栗行貴(20分)
16:00-16:20 セッション2 白井哲哉(20分)
16:30-17:20 パネルディスカッション
17:30 閉会
当日(11時~16時)は、茨城大学図書館において、企画展「東日本大震災と文化遺産-学生と市民が守ったふるさとの記憶-」も開催しております。あわせてご観覧ください。
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇第11回茨城大学人文学部地域史シンポジウムチラシ(JPEGファイル))
|
|
 2015.11 茨城大学図書館2015年度後学期企画展「東日本大震災と文化遺産-学生と市民が守ったふるさとの記憶-」(於茨城大学図書館)のご案内 2015.11 茨城大学図書館2015年度後学期企画展「東日本大震災と文化遺産-学生と市民が守ったふるさとの記憶-」(於茨城大学図書館)のご案内
2015年11月14日(土)から12月6日(日)まで、茨城大学図書館1階展示室において、企画展「東日本大震災と文化遺産-学生と市民が守ったふるさとの記憶-」が開催されます(※平日10時~16時・土日11時~16時、11月21日(土)と11月23日(月)は休館)。
この企画展は、茨城や東北各地で東日本大震災により被災し、学生と市民が救いだした文化遺産の中から、史料的価値が高く、また活動の特色をよく物語る資料を集め公開するものです。未曽有の大震災から四年半の歳月を経た今日、守られたかけがえのない文化遺産(文化財・歴史資料)を通じて、地域の歴史に接していただきたいと思います。アクセス方法や関連イベントなどの詳細については、添付のチラシ(PDF)をご覧ください。
茨城史料ネットでもこの企画展を後援しておりますので、ぜひ一度、足を運んでみてください。
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇茨城大学図書館2015年度後学期企画展チラシ①(JPEGファイル))
◇茨城大学図書館2015年度後学期企画展チラシ②(JPEGファイル))
|
|
 2015.3 茂木町資料整理活動終了のお知らせ 2015.3 茂木町資料整理活動終了のお知らせ
茨城史料ネットでは、2012年9月3日から、栃木県茂木町教育委員会の資料整理を支援していましたが、2015年3月30日の活動をもって定例の整理作業は終了となりました。
ご協力くださったみなさまに心より感謝申し上げます。
これからの旧島崎家資料の整理については、長期休暇中等に茂木町と協力しながら、集中的に進めていくことになると思いますので、引き続きのご支援、よろしくお願いいたします。
|
|
 2015.3 茂木町ふるさと歴史フォーラムⅡ「実像の茂木一族」開催のご案内 2015.3 茂木町ふるさと歴史フォーラムⅡ「実像の茂木一族」開催のご案内
2015年3月29日、茨城史料ネットは、茂木町教育委員会とともに、昨年開催された「茂木町ふるさと歴史フォーラム」の第二弾として、「実像の茂木一族―よみがえる「もののふ」たちの中世―」を開催いたします。
当会は、2012年から栃木県茂木町教育委員会の資料整理を支援しており、茂木町の歴史・文化財にかかわる事業を支援してきました。今回は、中世という時代をテーマに設定し、茂木町を舞台に活躍した「茂木氏」にスポットライトを当て、町の歴史をわかりやすくお伝えしたいと思います。
フォーラムでは、第一部として、江田郁夫氏に、茂木氏とその本領茂木荘についてご講演をいただきます。その後、第二部では、茂木氏の居城・茂木城跡等について、会場も交えて意見交換を行います。
また、3月28日(土)・29(日)は、茂木町民センター102会議室にて「茂木文書」(複製)7点を展示し、茨城史料ネットのメンバーが随時解説をいたします。
フォーラム・展示とも、どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ会場まで足をお運びください。フォーラムに関する詳細は、下記をご覧ください。
茂木町ふるさと歴史フォーラムⅡ「実像の茂木一族―よみがえる「もののふ」たちの中世―」
○日時:平成27年3月29日(日) 13時~16時
○会場:茂木町民センター 別館ホール(栃木県芳賀郡茂木町字茂木151番)
○入場:無料(先着200名様・申し込み不要)
○内容: 【第Ⅰ部】講演 「中世の茂木氏と茂木荘―南北朝・室町時代を中心に―」
江田郁夫氏(栃木県立博物館学芸部長)
【第Ⅱ部】ヒストリー・トーク 「茂木氏と茂木城を語る」
高橋修(茨城史料ネット代表 茨城大学教授)
山川千博(茨城史料ネット幹事 茨城大学大学院生)
○お問合せ:茨城大学人文学部高橋修研究室(osamu.takahashi.nzn@vc.ibaraki.ac.jp)
以下、開催をご案内するチラシが出来上がりましたので、こちらに掲載しておきます。ぜひご覧ください。
◇茂木町ふるさと歴史フォーラムチラシ(JPEGファイル))
|
|
 2015.2 歴史資料ネットワーク設立20周年記念「全国史料ネット研究交流集会」開催のご案内 2015.2 歴史資料ネットワーク設立20周年記念「全国史料ネット研究交流集会」開催のご案内
2015年2月14日(土)と15日(日)の両日、神戸国際会館(於:兵庫県神戸市中央区)において「歴史資料ネットワーク設立20周年記念「全国史料ネット研究交流集会」」が開催されます。
これは、歴史資料ネットワーク設立20周年となる節目の年に、災害時の資料保全に向けた連携を深めるため、日本各地の資料保全ネットワークが交流を行い、情報や保全の手法を共有する企画となっています。
当会もこれに後援として参加しており、2日目には当会会員による報告も行われます。また、当日の様子はインターネットで配信される予定となっておりますので、興味のある方はぜひお立ち寄りください。
なお、詳細な概要・プログラムについては、歴史資料ネットワークのホームページをご覧ください。
〇歴史資料ネットワーク設立20周年記念「全国史料ネット研究交流集会」(2/14・15)関連記事まとめ
|
 2014.10 「常陸太田市指定文化財集中曝涼(於:常陸太田市、常陸大宮市)」のご案内 2014.10 「常陸太田市指定文化財集中曝涼(於:常陸太田市、常陸大宮市)」のご案内
|
|
 2014.10 常陸大宮市文書館開館のご案内 2014.10 常陸大宮市文書館開館のご案内
◆茨城県内初!常陸大宮市に文書館がオープン!!
常陸大宮市文書館(ひたちおおみやしぶんしょかん)が、茨城県内初の市町村立の文書館として平成26年10月に発足しました。
文書館は、行政や団体が業務をおこなう過程で発生する文書を適切に整理、保存、管理し、文書を作成した組織の業務運営に生かすとともに、公開する施設です。また、個人の活動の記録である古文書や地区で発生・収受した文書(区有文書)等の地域史料を保存・管理する機能を持つ場合もあります。常陸大宮市文書館はこの2つの機能を併せ持つ施設です。
整理を終えた文書は、所定の手続きにより閲覧することができますのでご利用ください。
○開館日 平成26年10月10日(金)
○開館時間 午前9時~午後4時30分(申請は午後4時まで)
○休館日 毎週月曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
12月29日から翌年1月3日までの間
○入館料 無料
○お問合せ 〒319-2226 茨城県常陸大宮市北塩子1721
電話 0295-52-0571 Fax 0295-52-0851
Eメール bunsho@city.hitachiomiya.lg.jp
なお、詳細については以下のパンフレットをご覧ください。
◇常陸大宮市文書館パンフレットその①(JPEGファイル)
◇常陸大宮市文書館パンフレットその②(JPEGファイル)
|
|
 2014.3 茂木町ふるさと歴史フォーラム「歴史発見 茂木に生きた近江商人」 2014.3 茂木町ふるさと歴史フォーラム「歴史発見 茂木に生きた近江商人」
東日本大震災以後、民間の歴史資料救済団体である茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク(茨城史料ネット)は、茨城県内にとどまらず近隣諸県においても被災資料のレスキュー活動を行ってきました。
島﨑家は、江戸時代から茂木(栃木県芳賀郡茂木町)の地で近江商人として活躍した商家です。同家の土蔵におさめられた古文書・絵画・民具等は、その一つ一つが茂木の歴史をいまに伝える貴重な文化遺産です。しかし、昭和61年の大水害,平成23年の東日本大震災で土蔵が被災し、それらの保存もままならない状況となりました。茨城史料ネットでは、茂木町教育委員会から要請をうけて、これらの品々を土蔵から救い出し、よりよい状態で未来にのこしていくために必要な作業をすすめています。
フォーラムでは、近江商人・島﨑家の歴史を最新の研究成果とともに紹介するとともに、茨城史料ネットがすすめてきた島﨑家の被災史料の救出、整理作業の経過と、その成果について中間報告します。また、同会場にて、島﨑家の古文書・絵画・民具の展示会を開催します。今回のイベントを通して、地域の皆様・研究者の皆様に、茨城史料ネットの活動について広くご理解を深めていただきたく思います。
皆様方にぜひご来場いただきたく、ご案内申し上げます。
茂木町ふるさと歴史フォーラム「歴史発見 茂木に生きた近江商人-島﨑家の土蔵に伝わる文化遺産-」
日時:平成26年3月21日(金・祝) 13時~16時
会場:茂木町公民館 大ホール(栃木県芳賀郡茂木町字茂木151番)
入場:無料(先着200名様・申し込み不要)
内容:講演 江戸時代における北関東の近江商人―茂木町島﨑家の歴史―
鈴木敦子氏(大阪大学大学院経済学研究科資料室助手)
報告 茂木の文化遺産を守り伝えていく-島﨑家が受け継いできたもの-
茨城史料ネット
お問合せ:茨城大学人文学部添田仁研究室(029-228-8118 hitoshi.soeda.carp@vc.ibaraki.ac.jp)
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆茂木町【ふるさと歴史フォーラム】チラシ(JPEGファイル)
|
|
 2014.3 特別公開「のぞいてみよう島﨑家の蔵の中-救い出された近江商人の古文書・絵画・民具-」 2014.3 特別公開「のぞいてみよう島﨑家の蔵の中-救い出された近江商人の古文書・絵画・民具-」
特別公開「のぞいてみよう島﨑家の蔵の中-救い出された近江商人の古文書・絵画・民具-」
日時:平成26年3月21日(金・祝)~3月23日(日)10時~16時
会場:茂木町公民館1階会議室
※茨城史料ネットのメンバーが随時展示の解説を行います。
お問合せ:茨城大学人文学部添田仁研究室(029-228-8118 hitoshi.soeda.carp@vc.ibaraki.ac.jp)
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆茂木町【ふるさと歴史フォーラム】チラシ(JPEGファイル)
|
|
 2014.1 常陸大宮市歴史民俗資料館企画展「南郷道―水戸と奥州をつなぐもうひとつの道―」 2014.1 常陸大宮市歴史民俗資料館企画展「南郷道―水戸と奥州をつなぐもうひとつの道―」
常陸大宮市歴史民俗資料館で開催される「南郷道―水戸と奥州をつなぐもうひとつの道―」展に、
木造五大明王立像と天正17年10月30日付伊達政宗起請文(いわゆる政宗の「密書」)が展示されます。
前者は、大震災で堂舎ごと損壊し、茨城史料ネットがクリーニングや修復を支援した南郷道沿いの文化財です。
後者は、やはり震災で被害を受けたひたちなか市の商家の土蔵から救出され、茨城史料ネットが、保全・調査にあたった史料で、文中に「南郷」の言葉がみられます。
ぜひこの機会に、資料館に足を運んで実見してください。
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆常陸大宮市【企画展】チラシ表(JPEGファイル)
◆チラシ裏(JPEGファイル)
|
|
 2014.1 北茨城市歴史民俗資料館(野口雨情記念館)特別展示「発見!!土蔵の中の文化遺産(たからもの)」 2014.1 北茨城市歴史民俗資料館(野口雨情記念館)特別展示「発見!!土蔵の中の文化遺産(たからもの)」
東日本大震災の地震と津波で大きな被害を受けた北茨城市で、茨城史料ネットは、これまで様々な文化財・歴史資料の救済・保全活動に取り組んできました。
今回、そうした活動の中から新たに発見された史料が語る「北茨城の歴史」を、地元の皆様に紹介・説明する講演会と特別展示を開催します。
皆様のご参加、ご観覧をお待ちしております。
ふるさと歴史講演会「被災した歴史資料が語る 北茨城の歴史」
日時:平成26年2月8日 13時~16時
会場:北茨城市ふれあいセンター
講演:「地域の歴史資料を守ることの意義」(白井哲哉)
「蔵から飛び出した『飄軽者』、長久保紅堂」(西村慎太郎)
「鈴木主水と平潟商人」(井上拓巳)
「“発見”された敵討 ―平袖と平潟にて―」(添田仁)
※参加費無料、先着300名
北茨城市歴史民俗資料館(野口雨情記念館)特別展示「発見!!土蔵の中の文化遺産(たからもの)」
会期:平成26年1月28日~3月2日
会場:北茨城市歴史民俗資料館(野口雨情記念館)
入館料:一般・・・300円 団体(20名以上)・・・250円
学生(大学生まで)・・・100円 団体(20名以上)・・・80円
開館時間:9時~16時30分
休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)
野口雨情生家・資料館特別展示「長久保紅堂 ―雨情との友情―」
会期:平成26年1月28日~3月2日
会場:野口雨情生家・資料館
入館料:一般・・・100円
学生(中学生まで)・・・無料
休館日:年中無休
問合せ osamu.takahashi.nzn@vc.ibaraki.ac.jp
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆北茨城市【ふるさと歴史講演会】チラシ(JPEGファイル)
◆北茨城市【特別展示】チラシ(JPEGファイル)
|
 2013.9 台風18号による被災文化財についてのお願い 2013.9 台風18号による被災文化財についてのお願い
9月13日に発生した大型の台風18号は、15日から16日にかけて日本列島に上陸し、猛威をふるいました。この台風は広範な地域に被害をもたらし、茨城県内でも床上浸水やがけ崩れなど、豪雨による被害が発生しています。まずは、台風18号によって被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、亡くなられた方のご遺族に深くお悔やみを申し上げます。
あわせて、被災地の復旧に携われている災害ボランティアや自治体職員のみなさまのご尽力に敬意を表するとともに、被災地の一日も早い復旧・復興を、茨城史料ネットとしてお祈りいたしております。
茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク(略称:茨城史料ネット)では、現在、茨城県内ならびに周辺各地における文化財・歴史資料の被災状況について情報を蒐集しております。もし、指定・未指定にかかわらず、文化財・歴史資料への被害があった場合は、可能な範囲で情報をお寄せいただけないでしょうか。
また、もし旧集落・旧市街などが被災し、文化財・歴史資料の保全について、緊急の対処が必要な場合には、最低限の人員・資材・資金は用意しております。いつでも遠慮なくお声掛けください。
また、被災文化財・歴史資料の保全にあたっては、以下の点にご注意ください。
■水や泥で汚れた古文書は修復できる場合があります
さて、災害復旧の過程で、水や泥で濡れた古文書などが出てくることがあります。
これらは一見するとゴミのように見える場合がありますが、地域の貴重な歴史を記録したかけがえのない財産ですので、安易に処分しないでください。適切な処置法を行うことで、修復することが可能な場合があります。
■そもそも歴史資料って何?
「うちにはそんな古いもの・貴重なものなんてないわ…」とすぐに処分しないでください。国や県や市町村による指定文化財だけが歴史資料ではありません。
下記のようなものもムラやマチの歩みを示す貴重な資料なのです。
・古文書(くずした文字で和紙に書いたものなど)
・古い本(和紙に書かれて冊子にしてあるものなど)
・明治・大正・昭和の古い本・ノート・記録(手紙や日記など)・新聞・写真・絵
・古いふすまや屏風(古文書が下貼りに使われている場合がよくあります)
・自治会などの団体の記録や資料
・農具、機織りや養蚕の道具、古い着物など、物づくりや生活のための道具など
水や泥で汚れて一見するとゴミにしか見えないものでも歴史資料である場合があります。これらのものは捨てたり焼いたりせず大切に保管下さい。早急な処置によって、修復が可能な場合があります。
■どこにあるの?
これらのものは
・旧家の母屋や蔵、あるいはその中の木箱や和箪笥、長持など
・公民館のロッカーやその中の段ボール箱などに収められていることが多いようです。
■どこに相談すればいいの?
泥かきボランティアの方は、処分する前に所蔵者に確認してください。また史料所蔵者の方々も安易に廃棄・売却などせず、処置に困ったらお近くの教育委員会等にご相談ください。
行政の方々も復興業務で日々大変なご苦労があろうかと思います。ライフラインが復旧し、文化財業務に戻った段階ででも結構ですので地域の歴史資料の安否確認活動や被災史料の保全活動にご協力賜れば幸いです。
■濡れた資料はどう扱えばいいの?
歴史資料ネットワークのHP「水損資料の取り扱いについて」をご覧ください。
http://siryo-net.jp/%E8%B3%87%E6%96%99%E3%81%AE%E4%BF%AE%E5%BE%A9%E6%96%B9%E6%B3%95/
■なぜ保全する必要があるの?
茨城史料ネット(事務局・茨城大学人文学部高橋修研究室内)は、2011年に発生した東日本大震災の被災地で、歴史資料をはじめとした文化遺産の救出・保全をおこなってきた、歴史研究者と大学生・大学院生を中心としたボランティア団体です。
茨城県内の歴史学会や関係団体、自治体や市民のみなさまと協力しながら、地域社会の民間資料の救出や文化財の被害調査などに取り組んでいます。
私たちがこのような活動を行ってきたのは、災害が起きるとそれを契機に家や蔵に古くから置かれていた歴史資料が破棄・処分されてしまうことがよくあるからです。これまでも、私たちが駆けつけた時にはすでに歴史資料が処分された後であったということが何度もありました。
家々にはさまざまな形で家の記録や地域の歴史を伝えるものが数多く残されています。しかし、今回の水害により長く伝えられてきた古い文書や記録などがなくなってしまうとすれば、それは家にとっても地域にとっても残念なことといわざるをえません。
地域や家の歴史を復元するための唯一かつ貴重な地域の歴史資料の保全活動に、ご協力を賜れば幸いです。
|
|
 2013.4 特別公開「額田城に届いた伊達政宗の『密書』」 2013.4 特別公開「額田城に届いた伊達政宗の『密書』」
東日本大震災で被災した、ひたちなか市の商家の土蔵から、多くの美術工芸品、民具、古文書・古記録が発見され、その中に含まれる5通の古文書が、注目すべき新発見史料であることが判明しました。
5通は、いずれも奥州の戦国大名・伊達氏と、那珂市額田南郷に所在した額田城を居城とした小野崎氏との親密な関係を示す内容をもっていることから、かつては額田小野崎家に伝わった古文書の一部と思われます。
その中には、南進を狙う伊達政宗が、いまだ佐竹氏の傘下にあった小野崎昭通に遣わした「密書」とも呼ぶべき起請文も含まれています。5通の文書は、現在、他の史料群とともに、「茨城史料ネット」によって、保全・整理されています。
御所蔵者の御厚意と関係者の努力により、額田小野崎氏ゆかりの地・那珂市で、初公開されることになりました。
同時開催・写真展「3.11 被災した身近な文化遺産を守る取り組み」
今回発見された5通の古文書を含む資料群は、被災した所蔵者から茨城史料ネットが委託を受け、現在も保全と整理にあたっています。ボランティアの立場で文化財・歴史資料を守る取り組みとはどのようなものなのか、茨城史料ネットの活動を、写真パネルで紹介する写真展です。
茨城史料ネット事務局 高橋修(茨城大学教授)
問合せ osamu.takahashi.nzn@vc.ibaraki.ac.jp
029-228-8120(研究室直通)
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆那珂市【特別公開】【歴史フォーラム】チラシ(PDFファイル)
|
 2013.3 文化庁長官から感謝状をいただきました 2013.3 文化庁長官から感謝状をいただきました
茨城史料ネットは、「東日本大震災被災文化財等救援・修復活動への功労者」として、東北各県の史料ネット系団体とともに、文化庁長官から感謝状をいただきました。
3月25日、東京文化財研究所地下ホールにおいて行われた贈呈式に、事務局から高橋修・白井哲哉が出席し、近藤誠一長官から受け取ってきました。
3.11以来のレスキュー活動に参加してくれた院生・学生、自治体・博物館等の関係者、ボランティアの皆さんの御尽力により、受けることができた感謝状です。
これからも、ゆっくり少しずつ、地道に頑張りましょう。
贈呈式には高橋修(左) 白井哲哉(右)が出席し、文化庁長官から感謝状をいただきました。

茨城史料ネット事務局 高橋修(茨城大学教授)
問合せ osamu.takahashi.nzn@vc.ibaraki.ac.jp
029-228-8120(研究室直通)
|
|
 2013.2 鹿嶋市での歴史文化フォーラムと特別展示の開催について 2013.2 鹿嶋市での歴史文化フォーラムと特別展示の開催について
2013.2 鹿嶋市での歴史文化フォーラムと特別展示の開催について
2011年3月11日、鹿島港に流れ込んだ津波は、鹿嶋市と神栖市に大きな被害をもたらしました。鹿嶋市側では、旧長栖村住民の菩提寺で、貴重な文化財や歴史資料を所蔵する龍蔵院が被災しました。地元の皆さんの迅速な対応で流失は免れましたが、仏画や過去帳、古文書などが、水に浸かって大きな損傷を受けてしまいました。
貴重な文化財・歴史資料を救おうと、行政や研究者、ボランティアが立ち上がりました。文化庁や東京文化財研究所、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会、国宝修理装?師連盟等の指導・協力を受け、吸湿や防黴のための処置、資料の整理が行われました。保存処理は現在も継続中です。こうした立場を越えた多くの人々の努力により、文化財・歴史資料の損失は最小限に食い止められました。また作業の過程で、従来知られていなかった重要資料の発見もありました。
龍蔵院の文化財・歴史資料の救出は、行政と研究者あるいはボランティアという、異なる立場で文化財にかかわる関係者が連携を深める機会になりました。また龍蔵院の復興に尽力する長栖地区の住民の姿は、菩提寺に伝わる文化財や歴史資料が、住民の間の、さらには祖先と地域とを結ぶキズナでもあることを、あらためて示してくれました。
今回のフォーラムと特別展示が、鹿嶋市の津波被害の現実を忘れず、明日の防災を構想するため、そして津波から守られた文化財・歴史資料を通じて地域のキズナの意味を考える機会となれば幸いです。
茨城史料ネット事務局 高橋修(茨城大学教授)
問合せ osamu.takahashi.nzn@vc.ibaraki.ac.jp
029-228-8120(研究室直通)
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆鹿嶋市【歴史文化フォーラム】【特別展示】チラシ(PDFファイル)
|
 2012.11 茨城大学学園祭【特別展示】のご案内 2012.11 茨城大学学園祭【特別展示】のご案内
茨城史料ネットでは現在、東日本大震災で被災した文化財・歴史資料の救済・保全活動に取り組んでいます。11月10日(土曜)・11日(日曜)に開催される茨城大学学園祭「茨苑祭」で、保全を終えた救出史料の一部を展示・公開します。
展示史料は、学生たちが自分たちで選び、説明文や釈文を作りました。また学生たちがボランティアで参加した、これまでの歴史資料の救出・保全活動の様子を、写真パネルで紹介します。詳細は以下の通りです。
お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
◆茨城大学茨苑祭特別展示「震災を生き抜いた史料たち」
主催 茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース有志
日時 11月10日(9:30~17:30) 11月11日(9:30~17:00)
場所 茨城大学茨苑会館2階集会室2(茨城大学水戸キャンパス)
〈主な展示品〉
○安政4年屋敷絵図
○明治15年塩方調
○結び亀甲に鬼蔦紋陣羽織
○パネル展「茨城史料ネットの活動」
〔問合せ〕山川千博 yamakawachihiro@hotmail.com
※当日は駐車場に限りがありますので、ご来場の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
なお、詳細については以下のチラシをご覧ください。
◆学園祭【特別展示】チラシ(PDFファイル)
|
|
 2012.10 「指定文化財集中曝涼(虫干し一般公開)」の御案内 2012.10 「指定文化財集中曝涼(虫干し一般公開)」の御案内
10月20日(土)と21日(日)の両日、常陸太田市と常陸大宮市で、「指定文化財集中曝涼(虫干し一般公開)」が開催されます。
文化財を守り伝えて来た地元の皆さんが、年に一度の虫干しを兼ねて、土地の宝を公開する、文化財保護・公開の原点を感じることができる素晴らしい企画です。
茨城史料ネットではこの取り組みを支援しています。茨城県北部では、ちょうど紅葉も始まり、美しい季節を迎える時期です。どうぞお出かけください。
なお公開場所等の詳細については、以下の常陸太田市発行のチラシをご覧ください。
◆指定文化財集中曝涼チラシ(PDFファイル)
|
|
 2012.8 企画展「新治汲古館の継承~文化財レスキューの一事例~」の御案内 2012.8 企画展「新治汲古館の継承~文化財レスキューの一事例~」の御案内
桜川市の真壁伝承館歴史資料館において、第2回企画展「新治汲古館の継承~文化財レスキューの一事例~」が、7月28日より開催中です。新治汲古館は筑西市古郡に所在した私設の博物館です。在野の考古学者、故・藤田清氏が戦前より蒐集していた著名な考古資料が収蔵されていましたが、東日本大震災により収蔵庫が被災し、考古資料は桜川市へと一括寄託されました。
平成23年10月、文化財レスキュー事業の一環として、収蔵資料の桜川市への移送作業が行われ、この作業を、茨城史料ネットが全面的に支援しました。今回は、寄託資料の中でも特徴的なものが展示されます。また、展示室の一部で、茨城史料ネットの活動が、写真パネル等で紹介されています。さらに、茨城史料ネットのメンバーでもある田中裕氏(茨城大学准教授)による歴史講座も行われますので、ぜひ会場まで足をお運びください。
場所:真壁伝承館歴史資料館 (〒300-4408 茨城県桜川市真壁町真壁198)
期間:平成24年7月28日(土)~10月31日(水)
時間:9:00~16:30
休館日:月曜・祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日も)・年末年始
◆展示の詳細は以下の桜川市のHPからもご覧いただけます(チラシも閲覧可能です)。
http://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.php?code=2212
| |
 2012.5 竜巻被害速報
2012.5 竜巻被害速報
|
 2011.12 講演会・展示会のお知らせ 2011.12 講演会・展示会のお知らせ
来る12月14日、茨城大学において、茨城史料ネットのレスキュー活動についての講演を、事務局の高橋修が行います。また講演会に関連して、レスキュー活動の写真展と特別展示が開催されます。
講演会・展示とも、どなたでもご参加、ご来場いただけますので、ぜひ茨城大学まで足をお運び下さい。
※以下、茨城大学ホームページより一部転載
●講演会「東日本大震災で被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」
日時: 12月14日 (水) 14:00~16:00
会場: 茨城大学講堂 (水戸キャンパス内)
講師: 高橋 修 (茨城史料ネット事務局・人文学部教授)
※参加無料、事前の申し込み不要です。どなたでもご参加いただけます。
●関連展示
写真展「被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」
特別展示「襖の中のワンダーランド-救出された歴史資料から-」
日時: 12月14日 (水)~19日(月) 11:00~17:00
会場: 茨城大学図書館展示室 (水戸キャンパス内)
※入場無料。どなたでもご来場いただけます。
※詳細は下記のリンクよりお願い致します。
●茨城大学HPにイベント情報掲載
http://www.ibaraki.ac.jp/events/2011/11/281336.html
●茨城大学図書館HPニュースに掲載
http://www.lib.ibaraki.ac.jp/news/2011/1128/koen111128.html
|
|
 2011.11 ボランティア募集のお知らせ 2011.11 ボランティア募集のお知らせ
◆平潟レスキュー資料の整理ボランティア募集
9月のレスキュー活動で、北茨城市平潟の旧家の土蔵群から救出した歴史資料の整理・保全作業を、下記の要領で行います。今回は、近世~近代文書、民具などの整理が中心です。ボランティアで御参加いただける方は、茨城史料ネット事務局 高橋修osm@mx.ibaraki.ac.jp(@を小文字にして下さい)まで、お申込み下さい。
【日程】11月19日(土曜日)・同20日(日曜日)
【場所】北茨城市内資料一時保管場所
【集合】両日とも、9時20分 JR磯原駅、あるいは9時30分 北茨城市役所前
【その他】
・前日・当日の宿泊を希望される方はお申し付けください(実費)。
・ボランティア保険等に、各自、事前に加入してください。
・これまでに歴史資料を取り扱った経験をお持ちの方※には、歴史資料ネットワークから、先着順で、旅費・宿泊費の一部を助成していただけます(公共交通機関を利用し、かつ往復の交通費が4000円を越える方)。希望される方には「公募の書式」をお送りしますので、参加申込み時にあわせてお申し付けください。
※これまでに資料レスキューを経験された方、歴史講座・勉強会に参加した経験がある方、古文書や民具等の資料を用いた指導・実習を受けた経験がある方などです。ご自身が該当するかどうかお知りになりたい場合は、歴史資料ネットワークs-net@lit.kobe-u.ac.jp(@を小文字にして下さい)まで、お気軽にご相談ください。
|